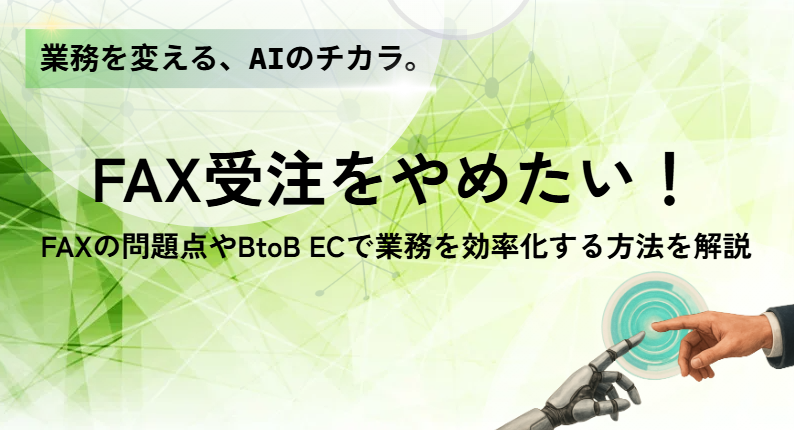
昨今では企業においてもペーパーレス化が進み、FAXに依存しない業務フローというものが求められているのが現状です。そんな中でもまだFAXを利用されている企業は少なくありません。しかし、業務負担を考えると「FAXでの受注をやめたい!」と思っている企業は多いのではないでしょうか。
今回は、FAX受注で起こる問題点や廃止できない理由、「BtoB EC」を活用して効率化する方法を紹介していきます。
FAX受注で起こる問題点
FAXでの受注業務は、依然として多くの企業で人手による処理が中心となっており、確認漏れや転記ミス、処理の遅延といったヒューマンエラーが発生しやすい環境にあります。これらのミスは、業務の正確性やスピードに悪影響を及ぼすだけでなく、担当者の精神的・時間的負担の増加や、特定の社員に依存する“属人化”のリスクにもつながります。こうした状況を放置すると、対応力の低下や引き継ぎの難しさといった課題が浮き彫りになります。では、FAX受注業務における具体的な課題を詳しく見ていきましょう。
業務が停滞する
FAXでの受注は、業務効率に影響を与える要因の一つといえるでしょう。受注内容を確認するために、受信したタイミングで席を離れて印刷物を取りに行く必要があり、そのたびに業務が中断されてしまいます。一度の作業は短時間ではありますが、回数が増えると大きな時間のロスにつながります。
さらに、取引先が多いほど確認作業の負担が増し、手作業による処理の遅れや確認にかかる時間が発生しやすくなります。加えて、一度席を離れると集中力が途切れ、再び業務に戻るまでに時間がかかるため、全体の生産性にも悪影響を及ぼします。FAX受注を続けることで発生する無駄な時間を削減し、業務のスムーズな進行を目指すことが重要です。
入力ミスが発生しやすい
FAXによる受注業務では、受信した内容を人の手で確認・入力する必要があるため、ケアレスミスや転記ミスといったヒューマンエラーが発生しやすいのが現実です。ミスの原因は必ずしも受注者側にあるとは限らず、発注書の筆跡が読みづらかったり、数字や品番が不鮮明だったりすることで、内容を誤って読み取ってしまうケースも少なくありません。その結果、本来受けるべき注文を見落とす「受注漏れ」や、数量・品番を間違えて処理してしまう「誤受注」といったトラブルが発生する可能性があります。こうしたミスは、納期の遅延や誤納品につながり、最悪の場合、取引先からのクレームや信用低下といった事態に発展する恐れもあるため、早急な対策が求められます。
検索がしづらい
紙ベースのFAX業務では、受信した書類がすべて物理的に保管されるため、パソコン上のデータのように簡単に検索や閲覧を行うことができません。例えば、過去の注文書や問い合わせ内容を確認したい場合、大量の紙の中から該当の書類を探し出し、その中から必要な情報を目視で確認しなければならず、多くの時間と労力がかかります。保管場所の確保や分類の手間も発生し、担当者によって管理方法が異なることで、探し方が属人化しやすいという課題もあります。こうした状況は、業務スピードの低下や情報の見落とし、二重対応といった非効率を引き起こしやすく、特に多忙な時期や人員が限られている現場では大きな負担となります。業務全体の効率化を図るには、FAXデータのデジタル化と検索性の向上が不可欠です。
コストがかかる
FAXによる受注業務では、紙やインク、トナーといった消耗品に加え、FAX機自体のリース代やメンテナンス費用など、日常的にかかるコストが多く発生します。さらに、FAXで受信した注文書の原本は取引証跡として一定期間保管する必要があるため、書類の保管スペースも確保しなければなりません。書類を分類・整理するための保管棚やファイルなどの備品費用もかかり、それに加えて書類の管理・検索・廃棄といった作業にかかわる人件費も無視できません。特に受注件数が多い企業では、書類が年々増え続け、保管スペースが逼迫するケースも少なくありません。こうしたアナログ運用は、目に見えにくいコストや負担を蓄積させており、業務効率と経営面の両方で大きな課題となっています。
テレワークに対応できない
従来のFAXは、専用の機器が設置されているオフィスでしか送受信ができないため、テレワーク環境との相性が非常に悪いという課題があります。FAXを確認・対応するためだけに社員が出社しなければならず、本来はリモートで対応可能な業務もオフィス常駐が前提となってしまいます。特に受注処理や問い合わせ対応など、時間の制約がある業務では、FAXの存在が柔軟な働き方を阻害する要因となり、テレワークの導入や推進を難しくしています。また、感染症対策や自然災害時の在宅勤務といった緊急時の対応力も低下するため、業務の継続性という観点でも大きなリスクを抱えることになります。FAX業務をデジタル化することは、単なる効率化にとどまらず、働き方改革やBCP(事業継続計画)の実現にも直結する重要な施策です。
会社がFAXを廃止できない理由
FAXによる受注業務は非効率と分かっていても、実際にはすぐに廃止できないケースが多くあります。特に取引先がFAX運用を続けている場合、自社だけでデジタル化を進めることが難しく、取引継続のためにFAX対応を続けざるを得ない状況が見られます。また、社内の業務フローや習慣がFAXを前提として構築されていることもあり、変更に対する抵抗感や調整の手間も大きなハードルとなります。ここでは、FAX受注がなかなか廃止できない主な要因をご紹介します。
業務を見直しが必要
FAXなどアナログな業務を中心に運用してきた企業にとって、FAX受注をやめることは単なるツールの入れ替えでは済まず、業務全体の見直しが必要になります。たとえば、FAXからデジタルへ移行するには、新たな受注管理システムやデータ連携の仕組みを導入する必要があり、初期コストや導入スケジュールの調整も発生します。また、これまで紙ベースで業務を行っていた社員にとっては、新システムの使い方に慣れるまでに時間がかかることも多く、操作研修やマニュアル整備などの教育体制も欠かせません。業務フローの変更には社内全体の理解と協力が不可欠であり、部門間での調整や習慣の見直しも必要となるため、移行には一定の準備期間と社内の合意形成が求められます。
取引先がFAXを希望している
FAX業務をデジタル化したいと考えていても、取引先がFAXでの対応しか受け付けていない場合、自社だけでFAXを廃止するのは現実的に難しいのが実情です。たとえ自社で受注管理システムやWeb受発注ツールを導入したとしても、取引先が従来通りのFAXを希望する限り、FAX対応を完全にやめることはできません。特に長年の付き合いがある顧客や、業界内でFAXが慣例化している場合には、無理にやめてしまうと信頼関係の悪化や取引停止につながるリスクもあり、顧客を失う恐れがあります。そのため、コストや業務負担を感じつつも、取引先の意向を尊重し、FAX対応を継続している企業が多く存在します。こうした背景から、FAX廃止に踏み切れないという状況は、単なる社内都合だけではなく、外部環境にも大きく左右されているのです。
IT化は必要ないと考えている
FAXは操作がシンプルで、特にITリテラシーが高くない方でも直感的に使えることから、「無理にIT化する必要はない」と考える企業も少なくありません。実際、年配の社員や現場中心の業務に従事している方にとっては、慣れ親しんだFAXの方が安心感があり、新しいツールの導入に抵抗を感じることもあります。しかし近年では、業務のデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が高まっており、企業としての競争力を維持・向上させるためにも、業務のIT化は避けて通れません。そのためには、単にツールを導入するだけでなく、従業員一人ひとりのITリテラシーを高める教育・支援も同時に行うことが重要です。今後を見据えた変革の第一歩として、FAXのデジタル化は有効なきっかけとなります。
FAX受注をやめたい場合に利用したいサービス
FAX受注による業務負担やミスのリスクを感じ、「FAXをやめたい」と考える企業は少なくありません。しかし、取引先の都合や社内業務の見直しが必要なため、すぐに廃止するのは難しい場合もあります。そうした企業が、段階的にFAX業務を効率化・自動化していくために導入を検討すべき主なサービスについて、以下でご紹介します。業務の現状に応じた最適な選択肢を見つけるヒントになれば幸いです。
受発注システム
受注・発注処理業務をデジタル化し、一元的に管理できる「受発注管理システム」は、電話やFAXに代わる新たな手段として多くの企業で導入が進んでいます。このシステムを活用することで、発注書の作成やデータ入力、受注内容の確認といった作業をすべてオンライン上で完結できるようになります。商品や取引金額の流れをリアルタイムで把握でき、業務全体の見える化にもつながります。これにより、人為的な入力ミスや確認漏れといったエラーの削減、対応スピードの向上が実現し、業務の効率化と信頼性向上を同時に図ることが可能です。特にFAX業務の見直しを検討している企業にとって、有力な選択肢となります。
EDI
受発注、請求、支払いなどの業務に関わる情報を電子化し、専用回線やインターネット回線を使って企業間でやり取りする仕組みが「EDI(電子データ交換)」です。紙ベースでのやり取りが不要になるため、郵送やFAXのような時間的ロスがなくなり、リアルタイムに近いスピードでの対応が可能になります。発注内容の誤記入や伝達漏れ、手配ミスといった人為的エラーのリスクが大幅に軽減されるほか、取引先とのやり取りがデジタルで記録されるため、情報の追跡や確認も容易になります。また、データの暗号化や認証機能を備えたEDIシステムであれば、情報漏洩などのセキュリティリスクにも対応でき、より安全な業務運用が実現できます。特に、大量の取引先と定型的な受発注を行っている企業にとって、業務の効率化と精度向上を両立できる有効な手段です。
ECシステム
BtoB向けECシステムは、普段私たちが利用する通販サイト(ECサイト)のようなユーザーインターフェースを備え、企業間での受発注をオンライン上で簡単に行える仕組みです。カート機能や注文履歴、在庫表示など、BtoCのECサイトでおなじみの機能に加え、掛け払い対応や取引先ごとの価格設定など、企業間取引に特化した機能も多数搭載されています。最近では、DXの流れを受けてBtoB ECサイトの導入が進んでおり、電話やFAXに代わる新たな受発注手段として注目を集めています。直感的な操作性により、ITに不慣れな担当者でも導入しやすく、業務の効率化と取引精度の向上が期待できます。
FAX業務は「BtoB EC」で効率化できる
FAXで行っていた受注業務は、「BtoB EC」を導入することで、大幅な効率化が可能になります。紙の注文書を使った手作業の処理が不要になり、取引先はWeb上で商品を選択・発注できるようになります。これにより、注文ミスや確認漏れといった人的エラーを削減できるだけでなく、リアルタイムでの受注処理が可能になり、対応スピードや業務の正確性も飛躍的に向上します。導入によって業務フローがスリム化し、社員の負担軽減や顧客満足度の向上にもつながります。
BtoB ECとは
「BtoB(Business to Business)」とは、企業が他の企業に対して商品やサービスを提供する取引形態のことを指します。一方、「EC(Electronic Commerce)」は電子商取引の略で、インターネットなどの電子的手段を使って商品やサービスを売買する仕組みです。つまり、「BtoB EC」とは、企業同士の取引において、インターネットを通じて商品やサービスの注文・販売を行うことを意味します。これにより、電話やFAX、メールといった従来のアナログな手段に比べて、取引スピードの向上や業務効率化、人的ミスの削減など、さまざまなメリットを得ることができます。近年では、BtoB取引に特化したECシステムの導入が進み、企業間の受発注業務のデジタル化が加速しています。
BtoB ECのメリット
これまでFAXや電話、メールなどを使って手作業で行っていた受注業務は、多くの時間と労力を必要とし、確認漏れや転記ミスといった人的エラーも発生しやすい状況にありました。こうしたアナログな受注業務をデジタル化・自動化することで、業務の効率化と担当者の負担軽減が実現できます。たとえば、注文内容の自動取り込みや在庫確認、納期調整といった作業をシステム上で完結できるようになれば、入力ミスや確認不足などのリスクを減らし、全体の業務品質も向上します。また、業務工程が簡素化されることで処理スピードもアップし、顧客対応の迅速化や満足度向上にもつながります。受注業務の改善は、DXの第一歩として非常に効果的です。
BtoB ECのデメリット
BtoB ECの導入には一定のコストがかかり、初期費用や月額利用料に加えて、既存システムとの連携やデータ移行にかかる手間や費用も発生します。また、自社の業務フローや取引形態がBtoB ECサイト構築用の標準パッケージと合わない場合、カスタマイズが必要となり、開発や調整に時間がかかることもあります。特に、取引先ごとの価格設定や独自の受発注ルールがある企業では、パッケージだけでは対応しきれず、追加開発が必要になるケースも少なくありません。そのため、導入を検討する際は、自社の業務にどこまで適応できるか、将来的な運用も含めて慎重に見極める必要があります。システム選定時には、柔軟性や拡張性も重視することが成功のポイントです。
BtoB ECサイトを構築する際のポイント
BtoB ECサイトを構築する際は、業務に合った機能や運用体制をしっかりと見極めることが重要です。取引先ごとの価格設定や承認フロー、在庫管理など、企業間取引ならではの要件に対応できる設計が求められます。スムーズな導入と効果的な運用を実現するために、構築前に押さえておきたいポイントを以下でご紹介します。
ECシステムに業務フローを合わせる
自社の業務フローに完全に合わせた形でBtoB ECサイトを構築しようとすると、多くの場合、システムのカスタマイズや追加開発が必要となり、結果として多額の導入コストがかかってしまいます。そこで重要になるのが、既存のECサイトの基本機能や提供されている標準パッケージに、できるだけ自社の業務を合わせていくという考え方です。すべてを一から作り込むのではなく、業務の一部を見直し、汎用的な機能の活用を優先することで、コストを抑えながらもスムーズな導入が実現できます。必要最小限のカスタマイズにとどめることで、運用開始までのスピードも早まり、結果として現場への負担も軽減されます。
既存の基幹システムと連携を前提にする
既存のシステムとBtoB ECサイトを連携させることで、在庫情報や顧客データ、受発注情報などをリアルタイムで共有でき、業務の正確性とスピードが大幅に向上します。特に、受注処理をよりスムーズに行いたい場合は、受発注業務の中心となる基幹システムとの連携を前提にECサイトを構築するのがおすすめです。手作業によるデータ入力や確認作業が減り、人的ミスの防止や業務の一元化にもつながります。
BtoB ECサイトにおすすめのプラットフォーム6選
MONO-X One
ノーコードでWebアプリケーションが作成できるプラットフォームです。受発注処理をWeb化してBtoB向けECサイトを運用したい企業や、仕入先向けの発注業務をWeb化したい企業におすすめです。FAXや電話などのミスや効率の悪さが目立つ取引において、作業工数や作業ミス、販売機会ロスをなくして基幹システムと直接連携してオンライン化をはかることができます。
MONO-X One の詳細はこちら
Bカート
「Bカート」は、月額9,800円から利用できるBtoB専用のクラウド型EC構築サービスです。取引先専用のログイン機能や、掛け払い・数量別価格設定といった企業間取引に特化した機能を標準搭載しており、BtoBビジネスに最適な自社ECサイトを手軽に構築できます。すでに累計2,000社以上の企業に導入されており、幅広い業種で利用実績があります。初期費用を抑えながらスピーディに導入できるため、FAXや電話、メールでの受注業務に課題を感じている企業にもおすすめです。業務効率化と取引先満足度の向上を同時に実現できる、注目のサービスです。
楽楽B2B
「楽楽B2B」は、企業間取引に特化したBtoB専用のECサイト構築サービスです。見積依頼や掛け払い、承認フロー、得意先ごとの価格設定など、BtoBに必要な機能を豊富に備えており、受発注業務を効率化します。さらに、決済代行サービスや送り状発行システム、在庫管理・販売管理ソフトとの連携にも対応しており、既存の業務システムとのスムーズな連携が可能です。クラウド型のため、初期費用を抑えてスピーディに導入できるのも特長の一つです。FAXや電話、メールによる受注業務に課題を感じている企業にとって、デジタル化と業務標準化を同時に進められる、実用性の高いサービスとして注目されています。
サブスクストアB2B
「サブスクストアB2B」は、BtoC向け定期通販システム「たまごリピート」の開発で培ったノウハウを活かして提供されている、BtoB専用のECプラットフォームです。企業間取引に必要な掛け払い対応、得意先ごとの価格設定、定期注文機能などを標準で搭載しており、柔軟な取引に対応可能です。特に定期・継続取引を効率化する機能に強みがあり、定期的な受注処理の手間を大幅に削減できます。また、既存の業務フローに組み込みやすい設計となっており、BtoBでもサブスクリプション型ビジネスを展開したい企業に最適です。受発注業務の効率化だけでなく、収益の安定化や業務標準化にもつながる注目のサービスです。
ecbeingBtoB
「ecbeing BtoB」は、高いカスタマイズ性と豊富な機能、そして強固なセキュリティが特長のBtoB専用ECプラットフォームです。業種や取引形態に合わせて柔軟に構築できるため、見積販売・掛け払い・会員制サイトなど多様な販売形態に対応可能です。既存システムとの連携もスムーズで、大規模な企業でも安心して利用できる実績あるサービスです。ビジネスの成長に合わせて拡張できる柔軟性も魅力です。
AladdinEC
「AladdinEC」は、30年以上にわたるシステム開発の実績を活かして設計された、企業間取引に特化したBtoB専用ECソリューションです。卸売業や製造業など、業界ごとの取引慣習や業務フローに応じた柔軟なカスタマイズが可能で、自社の業務にフィットしたECサイトの構築を実現できます。基幹システムとの連携や複雑な価格設定、多拠点管理にも対応しており、実務に即した使いやすさと高い拡張性を兼ね備えたサービスです。
受発注業務の未来を変える:FAXから始めるデジタル化戦略
FAX受注をやめたいと考えている企業にとって、BtoB ECサイトの導入は有効な選択肢の一つです。取引先とのやり取りをデジタル化することで、業務の効率化やミスの削減が期待できます。業務フローに合った機能を持つサービスや、カスタマイズ性の高いプラットフォームを選ぶことで、無理なく導入でき、コストも抑えられます。自社に最適なシステムを選ぶことが、FAXからの脱却とDX推進の第一歩となります。
MONO-Xでは、「MONO-X AI」を軸に、AIを活用した業務効率化やコスト削減をサポートしています。FAX業務のデジタル化から受発注業務全体の最適化まで、貴社にフィットするAI活用の方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
▼次世代のチャットベースAIデータ分析ツール「MONO-X AI」についてのお問い合わせ・ご相談はこちら
MONO-X AI 公式サイト
=================
▼基幹連携ノーコードSaaS「MONO-X One」についてのお問い合わせ・ご相談はこちら
MONO-X One 公式サイト
資料請求



