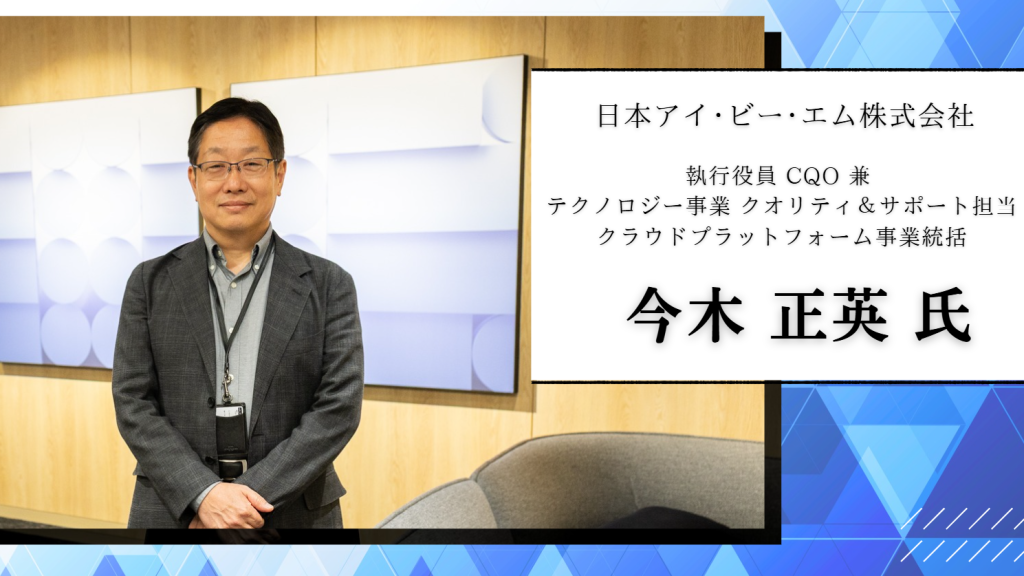
IBM i で稼働する基幹システムのクラウドリフトを支援する「PVS One」。そのPVS Oneを支える「人」にフォーカスしたインタビュー企画、「PVS One パートナーインタビュー」。第2回は、IBM Cloudの信頼性を支える日本アイ・ビー・エム株式会社の執行役員 CQO 兼 テクノロジー事業 クオリティ&サポート担当 クラウドプラットフォーム事業統括の今木氏に、弊社下野と中村がお話を伺いました。
クラウドを活用する上で最も重要なのは、何よりも品質管理とサポート体制です。信頼がなければ、アジリティやコスト最適化といったクラウドのメリットは意味を成しません。
さまざまなクラウドサービスが存在する中で、IBM Cloudはお客様の基幹業務を支えるクラウドとして、「透明性」「セキュリティ」「変更管理の精度向上」に特に注力しています。
今回は、これらの取り組みをリードされてきた今木氏に、IBM Cloudがどのように品質向上に取り組んでいるのか、変更管理やAIを活用した予測・予防戦略についても詳しくお話しいただきました。
本記事では、IBM Cloudの品質管理の裏側に迫るとともに、日本独自のサポート体制や、クラウド環境における最先端の取り組みを紹介します。クラウドの安定運用や品質管理に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
日本IBMにおける品質とサポートの取り組み
【下野】
本日はインタビューの機会をいただきありがとうございます。IBM Cloudの裏側についてお話を伺えるとのことで、大変楽しみにしておりました。
弊社では基幹システムのクラウド化に注力しており、お客様にクラウドへ一歩踏み出していただくために最も重要なのは「安心感」だと考えています。IBM Cloudと関わる中で、その信頼性が日々向上していると実感しています。
本日は、品質管理をご担当されている今木様に、IBM Cloudでどのような取り組みを行っているのか、特に品質に厳しい日本のお客様へどのように安心をご提供されているのか、お話を伺えればと思います。
まずはじめに、今木様がどのようなお立場でお客様をご支援されているのか、お聞かせください。
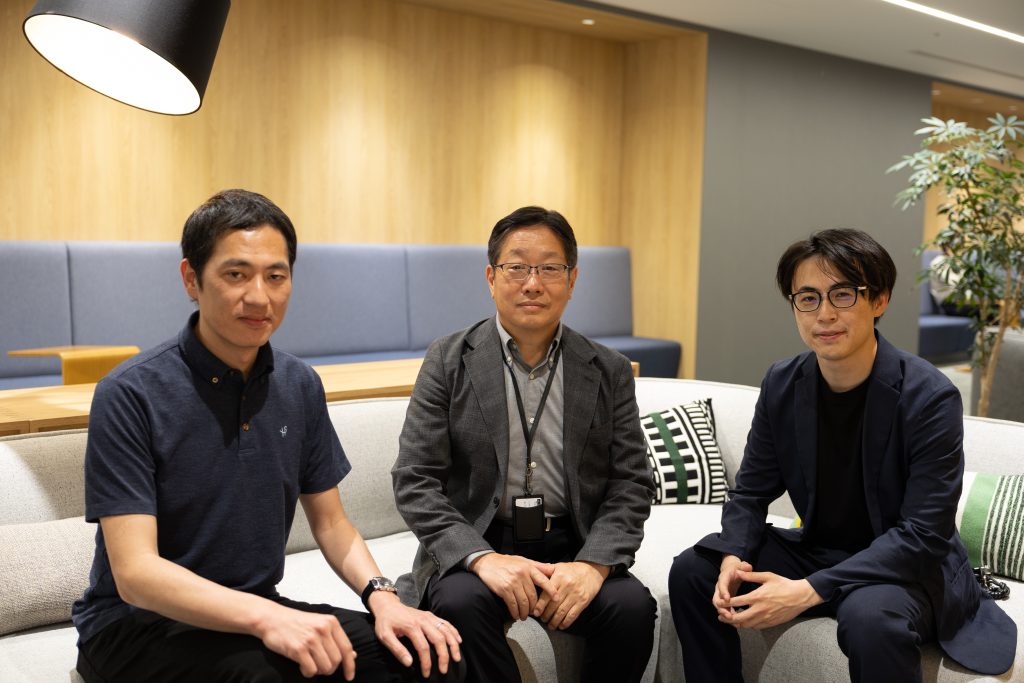
【今木】
私は日本IBMにおける最高品質責任者を務めています。サポート対象はクラウドに限らず、IBMのテクノロジー製品全体――ハードウェア、ソフトウェア、クラウド、SaaSなどすべての領域にわたり、品質とサポート対応を行っています。
主に以下の2点に注力しています。
1つ目は、トラブルが発生しない仕組みづくりです。事前に問題を防ぐ取り組みはもちろん、想定外の事象が発生した際にも、迅速な解析と対応ができるようなプロセスを構築しています。
2つ目は、情報の共有による予防です。過去の事例やヒヤリ・ハット情報を社内で共有し、トラブルの未然防止に努めています。これらの活動を通じて品質とサポートの向上を目指し、全社的に展開しています。
また、お客様との直接のコミュニケーションの場も設けており、IBMの取り組みをご説明するだけでなく、改善に向けたご意見を伺う場として活用しています。こうした活動を通じて、品質についての全体的なリーダーシップも担っています。
日本のお客様に向けた品質管理とサポートへの取り組み
【中村】
品質管理について、特に要求が厳しい日本のお客様に向けたサポートの取り組みについてお伺いします。欧米と日本では、ITに対する品質管理の考え方にも違いがあるように感じています。日本のお客様によりご満足いただくために、どのような工夫や対策をされているのでしょうか?
【今木】
日本のお客様に対しては、特に変更管理に重点を置いています。というのも、何らかの変更を加えると、必然的に問題が発生するリスクが高まるためです。そのリスクを最小限に抑えるため、変更管理のプロセスをより厳格にし、慎重に進めることを意識しています。
もちろん、インフラ面の改善、たとえばネットワークや最新アーキテクチャの導入といった取り組みも継続的に実施しています。これらの領域はすでに一定の品質水準に達していますが、変更は常に発生するものであり、その際にいかにリスクを事前に排除できるかが鍵になります。
変更管理において特に注意しているのは、「過去に何度も実施しているから大丈夫」という過信を排除することです。そこで、変更管理の対象範囲を拡大し、より広範囲の変更についても慎重に確認する体制を整えています。
また、変更管理のプロセスをより強化するために、米国チームに一任するのではなく、日本チームも積極的に関与できる体制を構築しました。具体的には、米国チーム内に日本メンバーをアサインし、変更の計画段階から実施状況の確認まで、一貫して把握できるようにしています。これにより、日本チームと米国チームが一体となって変更管理に取り組む環境が実現しました。
さらに、日本チームは変更管理ボードにも参加し、米国側と日本側が同じ場で「指差し確認」を行いながら重要事項を共有しています。このような取り組みによって、変更に伴うリスクを確実に管理し、品質向上を実現しています。

【中村】
なるほど。これは地域ごとにそれぞれの担当者がいらっしゃるのでしょうか? それとも、日本の担当者という観点でのご対応なのでしょうか?
【今木】
国単位で独立したサポートチームを設けているのは、日本だけです。もちろん、グローバルチームと密接に連携しながら推進していますが、日本には独自のサポートチームがあり、米国チームと協力しながら対応しています。この体制は日本発の試みですが、現在は非常にうまく機能しており、他地域でもこのモデルを参考にしようという動きが広がっています。
【下野】
やはり、その背景には日本のお客様とグローバルのお客様で、品質に対する考え方や捉え方の違いがあるのでしょうか?
【今木】
おっしゃるとおりです。たとえば金融業界のお客様であれば、欧米企業でも高い品質が求められる傾向にありますが、日本のお客様は特に、「なぜそれが起こったのか?」という原因の追求や、「同じことが再発しないよう担保されているのか?」という視点で、非常に厳格に品質を確認されます。こうした背景から、より慎重かつ丁寧な対応が求められるため、日本独自の体制を整える必要がありました。
【下野】
グローバルに展開されているサービスを日本企業が利用する際には、どうしても欧米のスタンダードに合わせざるを得ないことが多いと感じています。しかし、日本IBMが、そうした考え方の違いを踏まえた独自の取り組みをされているということは、日本のお客様にとって非常に安心材料となるのではないでしょうか。
クラウドならではの品質管理の難しさとその取り組み
【下野】
IBM Cloudは、他のクラウドサービスと比較して、基幹システムを支えるクラウドとしてお客様の期待が特に高いと感じています。クラウドサービスは、多くのサービスが複雑に連携しているため、品質管理の面でも難しさがあると思いますが、その点についてはどのような取り組みをされていますか?
【今木】
先ほどの話と一部重複しますが、IBM Cloudでは、日々非常に多くの変更が行われています。実際、世界中のどこかで常に何らかの変更が発生している状況です。これは、データセンターの数が多く、利用しているお客様も多岐にわたるためです。つまり、多くの変更が常に同時進行しているのです。
このような状況の中で、すべての変更を細部まで完全に管理するのは現実的に不可能です。そのため、変更管理の対象範囲を広げつつ、特にリスクの高い変更に重点を置いて管理しています。具体的には、影響が大きい変更を事前に特定し、しっかりとレビュー・対策を講じる体制を整えています。

たとえば、DNSの管理がその一例です。DNSは非常に成熟した技術であり、多くのエンジニアがその仕組みを理解し、手順も確立されていますが、一度ミスが起これば、影響は非常に広範囲に及びます。そのため、DNSに関わる変更は特に慎重に取り扱っています。
また、異なるリージョンで発生した問題にも注目しています。各データセンターに同じ変更を適用する際、たとえそれが日本以外での事例であっても、同様の問題が日本でも発生する可能性が極めて高いと認識し、そうした変更については特に厳格に対応しています。
さらに、仮想化技術やコンテナの普及により、クラウド環境は非常に複雑な構成になっています。一見関係のないメンテナンスでも、思わぬ部分に影響を及ぼす可能性があります。そのため、変更の影響範囲は常に広く見積もり、新しい要素が加わる際は、リスクがあるものとしてより厳格にレビューを行っています。
こうした変更管理において、特に重視しているのが以下の3つの評価軸です:
1.変更による影響度
その変更がシステム全体にどの程度の影響を及ぼすのかを事前に評価します。
2.変更の実施方法
自動化されているか、人手による操作が含まれるかによって、リスクの大きさが変わります。
3.他リージョンでの問題発生状況
他のリージョンで同様の変更が行われ、問題が発生していないかをチェックします。
この3つの軸に基づいてスコアリングを行い、変更のリスクレベルを判断しています。すべての軸でリスクが高いと判断された場合、その変更作業自体を完全に中止する判断を下すこともあります。
一方で、1つまたは2つの評価軸でリスクが高いと判定された場合には、ただちに作業を止めるのではなく、追加のレビューを実施します。具体的には、技術者によるレビュー・審議を行い、必要に応じて再度テストを実施。その結果をもとに「GO(実施)」または「NO GO(中止)」の最終判断を下しています。
【中村】
なるほど。たとえば継続が困難と判断された場合には、一部を自動化したり、影響度を下げる方法を検討したりして、何らかの形で前に進めていくという形になるのでしょうか?
【今木】
そのとおりです。また、デプロイメントの履歴も非常に重要な判断材料になります。過去に他の環境で同様の変更を行った際に問題が発生していた場合、その問題に対する恒久対応が完了し、すでに解決されているかどうかを厳密に確認します。 このような過去の実績が少なくとも一度確認されていれば、ようやくリスクを低減できたと判断し、対応を進めることができます。対象は、サーバー、ネットワーク、ストレージといったあらゆる要素に及びます。
変更管理の精度を高めるためのAI活用と予測・予防戦略
【下野】
昨今、AIがさまざまな分野で注目を集めています。品質管理の領域においても、AIを活用されている部分はありますでしょうか。
【今木】
はい。私たちはAIを予測や予防の観点で積極的に活用しています。
これまでご説明してきた通り、従来から「トラブルゼロ」を目指して、さまざまな取り組みを進めてきました。たとえば、問題が発生した際には、これまで通りレビュー会議を実施し、事象を分析して改善策をフィードバックするというプロセスを継続しています。しかし現在はそれに加えて、問題の予兆を事前に検知し、未然に対応できる体制の強化にも注力しています。
具体的には、リアルタイムでのシステム監視を行い、異常の兆候をいち早く検知して初動対応を自動で実施する仕組みを導入しています。異常が検出された際にはアラートが発せられ、状況に応じて人の判断を介してシステムを停止させることもあれば、AIによって自動的に初動対処を行い、問題の拡大を防ぐケースもあります。
さらに、こうした対応によって得られたデータや知見をもとに、機械学習による再学習を行っています。具体的には、発生した問題とその解決策を学習データとして蓄積し、AIモデルにフィードバックして再トレーニングを実施。このプロセスを継続的に繰り返すことで、予測精度と対応精度の向上を図っています。
こうした継続的な改善の仕組みにより、監視および対応の精度が大きく向上し、結果として全体的な品質の底上げにつながっています。
【中村】
こうしたAIを活用した仕組みは、グローバル全体で整備されているのでしょうか?
【今木】
はい。これらの取り組みは、クラウド基盤を統括している米国のコアチームが専任で担当しています。彼らは常にシステムを最新の状態にブラッシュアップしながら、グローバルな品質向上を目指して日々改善を重ねています。
品質管理の精度を高めるために—IBM Cloudが実践する意識共有の取り組み
【下野】
最後に、高い精度の品質管理を実現する上で、チーム作りやマインドセットの醸成という観点で、実践されていることがあれば教えてください。
【今木】
これは少し精神的・文化的な側面になりますが、私たちが重視しているのは、「ベスト・プラクティスの共有」と「品質意識の共通化」です。
| ディプロイメント・メソドロジーからリスクを排除 | 最悪のシナリオを想定した計画 | 「エンタープライズサービス」の精神を持つ |
| より小さく安全な変更 | 全ての変更に対して4つの目によるレビューが必要 | ビジネスオーナーとして考え行動する |
| 展開後の検証は必須 | 実施後の点検 | リスクを含む変更は地域の営業時間に実施すべきではない |
見ていただくと、一見すると“当たり前”のことのように思われるかもしれません。しかし、一般的な組織と同様、IBM Cloudのチームも、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成され、入れ代わりもあります。
そのようなメンバーが協業する環境においては、“当たり前”の基準すら、個人ごとに違っている可能性があります。
そこで私たちは、9つの原則を共通のルールとしてチーム全体に展開し、品質に対する意識を統一することを重視しています。
クラウドチームでは、常に新たなメンバーの加入や、サービス拡張に伴うチームの再編成が行われています。入社のタイミングやキャリアパスが異なるメンバーが、それぞれの専門領域において共通認識のもとで行動できるよう、クラウド運用において守るべきルールを明文化・共有することが不可欠なのです。
これは、製造業の工場現場に掲示されている「安全ルール」と同じ役割を担っています。クラウド運用という“目に見えない現場”においても、明確な手順と基準を全員で共有することで、運用の一貫性と品質が保たれるのです。この共通認識こそが、クラウド基盤を安定的に提供し続けるための土台になっています。

また、IBM Cloud全体を統括している米国本社の責任者は、金融業界で長年クラウド運用に携わってきた経験を持つ人物です。だからこそ、「お客様の重要な基幹業務を支えている」という意識を、すべてのメンバーが強く持つことを重要視しています。
単に技術的なミスを防ぐだけでなく、お客様のビジネスを止めてはならないという“責任感”を全員で共有し、それを徹底的に守る。この姿勢が、IBM Cloudの品質管理における原動力となっています。
この取り組みは、特定の部署に限られたものではありません。
データセンターでのオペレーションを担当するスタッフ、ネットワーク設定やテストを行うチーム、サーバー管理に携わるチームなど、IBM Cloudのすべてのグループが同じ方針のもとで動いています。
このように、全体的な意識統一と運用基準の明確化により、IBM Cloudでは“グローバルで一貫した品質”を実現しています。
IBM Cloudの強み : 透明性とセキュリティ
【中村】
今木様のご見解として、IBM Cloudの強みはどのような点にあるとお考えでしょうか?
【今木】
IBM Cloudの最大の強みは、「透明性」と「セキュリティ」に対する徹底した取り組みにあると考えています。これらは、お客様の基幹業務を安心して預けていただけるクラウド環境を構築するうえで、非常に重要な要素です。
まず、「透明性」の観点では、IBM Cloudではサーバーの設置場所やネットワーク構成に関する情報を、可能な範囲で開示しています。これにより、お客様は自身のデータ資産がどこに存在しているのかを、明確に把握することが可能です。完全な開示が難しい領域もあるものの、ホスティングに近い管理性を実現している点は、他クラウドにはない大きな特長だと考えています。
次に、「セキュリティ」については、クラウド基盤そのものの強化に重点を置いています。IBMのSOC(Security Operation Center)と連携しながら、全体のセキュリティ監視とインシデント対応体制を構築しており、インフラレベルから安心してご利用いただける仕組みを整えています。
加えて、サービスメニューにも高いセキュリティレベルを反映させています。たとえば、IBM Zの暗号化技術などを活用したサービス群により、お客様のセキュリティポリシーに合わせた選択が可能です。
こうした取り組みを通じて、IBM Cloudは「安心して基幹業務を任せられるクラウド」として、多くのお客様にご信頼をいただいています。
柔軟なクラウド活用への新たな一歩を
【下野】
最後に、MONO-X でご支援している IBM Cloud や PowerVS をご利用されているユーザー様やこれから検討されるユーザー様に向けて一言、お願いいたします。
【今木】
IBM Cloudは、「透明性」「セキュリティ」、そして「基幹業務を預かる責任」を極めて重視したクラウドサービスです。特に、PowerVSをご利用のお客様は、基幹系システムでの活用が多いと認識しています。そのため、オンプレミスと同様の安定した環境をクラウド上で実現できる点は、IBM Cloudならではの強みです。
私たちは、従来のx86ベースのクラウドサービスに加え、IBM Powerとのハイブリッド活用を可能にする柔軟な基盤をご提供しています。これにより、お客様の多様なニーズに応じたクラウド活用を実現できます。 今後もこの仕組みをより多くのお客様にご活用いただき、安心・安全かつ高品質なクラウド環境の提供に向けて、品質管理の取り組みと運用体制の強化を継続してまいります。
弊社製品「PVS One」を活用すれば、IBM Cloudの導入が初めてでも、安心して移行・運用・活用が可能です。IBM i やIBM Cloudに精通したメンバーが全面的にサポートいたします。ぜひ、PVS Oneの導入をご検討ください。
PVS Oneに関するお問い合わせはこちら

|
インタビュアー 一橋大学卒業後、日本IBM入社。10年間 IBM i 統括部などで営業や事業開発を経験。2020年当社に入社し、同年6月 取締役に就任。2025年6月12日付で代表取締役社長に就任。 |

|
インタビュアー 2003年に日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリングへ入社。2004年よりIBMグループ内の各部門にて、IBM i を主たる技術エリアとして提案段階からプロジェクト実施に至る各局面における技術支援を担当。2024年4月にMONO-Xに入社し、新規ソリューションや機能の検証、お客様環境への適用、クラウド環境の技術支援など、前職での経験も活かした活動を担っています。 |



